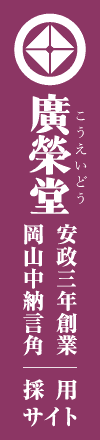短期合宿でとことん話し合った、
パッケージが完成するまで
お話をお伺いした方

社長室 商品開発担当(現在)
奥村朋子
2013年入社
東京都出身
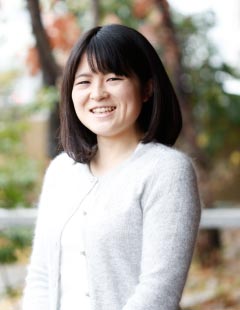
社長室 経営特区(現在)
竹本明日香
2014年入社
愛知県出身

廣榮堂商品のパッケージリニューアルが始まった経緯は?
奥村:以前から売場の声として「廣榮堂の和菓子を永くご愛顧いただいているお客さまに加えて、より若い方にも手にとってもらえる包装があるといい」との意見は挙がっていました。またそのためには、一度東京など大都市で知恵を磨いた感性豊かなデザイナーの方と共に話し合う機会があるとよいのでは、との考えがありました。そこで、「いつか一緒に何かできたらよいですね」と仰ってくれていたあるデザイン会社にお声がけし、思い切ってパッケージを刷新するプロジェクトが立ち上がり、そこに私たちふたりも加わったかたちです。
それぞれ、どんな立場から参加したのですか?
奥村:私は東京から転職してきて、廣榮堂では商品開発を担当しています。前職ではパンの商品開発をしていましたが、今回のようなパッケージは新領域の挑戦でした。ただ、同じチームにキャリアの長い店長や本社スタッフ、また販売や製造のメンバーもいたので、心強さはありました。
竹本:私は入社後しばらく店舗での販売を経験してすぐ、チームに合流しました。振り返ると、そういう立場ならではの「外の目線」を期待されたのかなと感じます。
デザイナーの方と廣榮堂との話し合いは、どんなふうに始まったのですか?
奥村:まず、瀬戸内市の前島にご担当お二人をお招きし、2泊3日の「合宿」を行いました。先方から「最初に廣榮堂の全商品パッケージを並べて話し合いましょう」とご提案があり、「それでは、瀬戸内海を見ながら合宿はどうですか?」とお誘いしたんです。ここには弊社が新人研修で毎年使わせてもらう宿があり、お互い他の業務から離れ、集中して意見を交換・共有できると考えての提案でした。

実際はどのような展開になったのでしょう?
奥村:現パッケージの課題を、遠慮なしに伝え合う場となりました。それは商品名にまで及び、たとえば「天恵萬菓(てんけいまんか)」のような重厚なイメージの名称を、より親しみやすい「どらやきと一乃栗」に変更することも後に実際に行われました。同じ釜のご飯を食べる合宿を通じ、社内外の垣根を越えて良いものをつくろうという想いを早期に共有できたのは大きかったと感じます。
リニューアルのコンセプトは?
奥村:その後、プロジェクト全体を貫くシンプルなコンセプトとして、デザイナーの方から「岡山の顔」「美味しい顔」という2案を頂きました。どちらも廣榮堂の想いを汲み取ってくださったものですが、製造の現場から「自分たちの誇りは突き詰めれば“美味しいものづくり”にあると思う」との言葉が決め手で、「美味しい顔」が選ばれました。
これをもとに、新パッケージ群がデザインされたわけですね。
新パッケージ群
モチーフは各和菓子そのものを選び、軽やかなイラストと明るい色調で刷新。上箱の下部中央から伸びる白帯に商品名を記す独特なデザインは、店頭で陳列した時などにも廣榮堂ブランドがひと目でわかるアイデア。2014年に5品、2015年は3品がリニューアルされ、該当商品の売上は順調な伸びをみせている。
奥村:お菓子そのものをモチーフにした繊細で楽しげなイラストや、他社製品と並んでもひと目で廣榮堂とわかる統一感など、とても良い案が頂けました。でもそこからが大変で――というのは、色味のこだわりがチーム内でも本当に様々だったんですね
竹本:「涼しげで夏にはよいけれど、冬は売れないのでは?」「単体では良さそう。でも、いくつか並べたときこの色はどうかな?」など、意見はまさに十人十色でした。とくに難航したのが『きび大福』の背景色決めです。廣榮堂側の希望でピンクを選びましたが、同じ「ピンク」でも本当に多様な色があり、複数案を持って販売店を回り、現場の声を聞くこともしました。最終的に「一斤染」という色(日本の古色名。紅花で染めたやや淡い紅色)に決まりました。
奥村:お店ごとの照明でも見え方は変わるんですよね。当然ですが、全員の意見をもれなく汲み取ることは不可能です。ただ「お客さまも他の社員も、私たちが迷いながら決めたパッケージなんて嫌だろうな」と思い、最後は「これだ」と信念を持って決めるべきだと気付きました。それがこの仕事を託された者の責任でもある、と気持ちを切り替えたことで、良い決断ができたと思います。実際に「きび大福」をはじめとして、リニューアル後は売上も伸びていて嬉しいですね。デザイナーの方も自分たちのことのように喜んでくださって、こうした積み重ねが廣榮堂の新しい「顔」に育っていけばと思います。

パッケージに記す商品名の文字や、しおりの文章もすべて新たに用意していますね。
奥村:商品名は、書家の方に実際に和菓子各種を召し上がっていただいた上で、書いていただいたものです。菓子箱に入れるしおりは、竹本さんともうひとりの新人で担当しましたね。
竹本:先輩から「しおりはお客さまがお菓子を召し上がりながら気軽に見るもの。言葉が多過ぎてもいけない」とアドバイスされ、個々のお菓子の成り立ちを学ぶことから、どんな形容詞なら美味しさが伝わるのかまで、試行錯誤が続きました。しばらく図書館通いの日々でしたが、あるとき「会社にも過去のしおりの制作資料があるはず」と助言をもらい、実際そこには先輩たちが残してくれた資料が沢山ありました。その経験があったのでしおりが完成したとき、自分の経験も資料に加えてみました。

現在までに和菓子8種のリニューアルが完了し、今後も続く予定です。プロジェクトを通じて得たやりがいはありますか?
竹本:私は愛知県出身で、大学は北海道でしたが、そこで偶然出会った廣榮堂のお菓子に惹かれて入社した経緯があります。また、販売員のときは駅の売場担当で、お土産を探して一期一会的にそこを訪れる人も多いと感じたことがありました。そう思うと、お客さまとお菓子が出会う大切なきっかけになるパッケージに関われたのは、大きなやりがいでもありました。また、一人ひとりが進めた動きがひとつに結晶する魅力を体験できたのも、このプロジェクトで得たものです。
奥村:自分が以前にパンの商品開発をしていたころは、いわば私が「中身」を作っているんだという気持ちがありました。でもこのプロジェクトで、商品とはそれだけではない、開発したレシピを実際に製造する人、パッケージをつくる人、それを各地に届ける人など、みんなの力でできているのだと実感できました。今後もこの経験を大切にしたいと思っています。